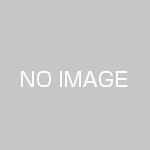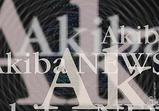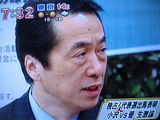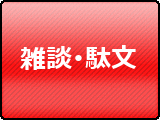マンガは現在、本の中でもトップクラスの発行部数で、週刊系のジャンプ、マガジン等の発行部数をあわせれば、一月で日本の人口を上回るんじゃないかと…。そこで、ここまで大きく発展すれば当然これについての学問を!と考える人が出てくるわけでして。今回は、そんな巨大市場に発展したマンガは学問になるのか?などなど…というハナシです。
マンガは現在、本の中でもトップクラスの発行部数で、週刊系のジャンプ、マガジン等の発行部数をあわせれば、一月で日本の人口を上回るんじゃないかと…。そこで、ここまで大きく発展すれば当然これについての学問を!と考える人が出てくるわけでして。今回は、そんな巨大市場に発展したマンガは学問になるのか?などなど…というハナシです。
マンガといえば…なんていったら、今は千差万別、十人十色の返答が返ってくるでしょうが、昔はそうじゃなかったようですね。かの巨匠、手塚治氏の名前が返ってきたわけで。
氏は、ありとあらゆるマンガを描いてます。ロボ、ヒーロー、サバイバル、宗教、医療、ふたなり…。
もうバージンスノーは残ってない状態であることは間違い無さそうですね。そうなってくると、良く似たマンガを描くしかなくなります。しかし、その中でも売れるマンガと売れないマンガが出てきます。その傾向を調べることが学問になるんだそうです。
つまり、マーケティング戦略なんですかね。
ドラえもん学なるものもあるそうですので、これを見習ってもっと小分けしてみてはいかがでしょうか?
スクラン学、ネギま!学、アカギ学、げんしけん学…。
いくらでも出来そうですが、本当のファン同士が集まって、ガチャガチャ議論する中で生まれるものもあるでしょう。
偉い大学の教授達はこういった学問は低俗だ。とする人が多いようですね。
何の役にもたたないのだとか。果たしてそうなんでしょうか?地質とか水質を調べるよりも低俗?法律が全てであり他の学問はその下位?経済学で全て説明がつく?
おそらく学問には上下の差はないでしょう。既得権や保身のためにそんなことを言っているだけ。
ならば、マンガ学…「作品名」学があってもいいはずです。
役に立たない学問などまずありません。何かしらに役立ちますし、使いようだと思いますよ?
オタクが集まって学問とはけしからん!
と言う人もいるでしょう。
でも、法学は法学オタクが、経済は経済オタクが、工学は工学オタクがやっているわけで、大差はない。そうして、どんな学問も最初は数人の学者から始まっているのです。
私はマンガ学のみならず、オタク文化全てが学問に適していると考えています。
オタク経済学、オタク心理学、オタク文学なんてのがあっても良いでしょう。
科学者気取りでマンガを読んでみるのもいいかもしれませんよ?
その結果、この学問が発展するかもしれませんし、それを強く願っています。
俺もオタク学者になるかって方は是非ワンクリを~。
人気ブログランキング ←ぽちっと押して下さると、狂喜乱舞します